発見されたノアの方舟と本当のシナイ山
コチラに残っていた記事から復活です。
ドキュメンタリー「本当のシナイ山」日本語字幕;以下は
エジプト記 No.3 神の山ホレブ
からの引用です。
モーセが住んだミデヤンは古代の歴史地図でも現在のアラビヤ半島のサウジアラビヤ西部にあった国です。モーセはそこで羊を飼っていたときに、神の山と呼ばれるホレブ山の麓にやってきました。
そこに不思議な光景がありました。
柴が燃えているのに燃え尽きなかったのです。
これはモーセを招く神様の方法でした。
出エジプト記3:1〜5
□ホレブ(シナイ)山はどこにあったか
現在、ホレブ山はシナイ半島の先端にあるジェベル・ムーサ(モーセの山)と言われています。
そして、それが当然のようにキリスト教系の出版物や旅行社のパンフレットに書かれています。そして毎年多くの観光客がそこに行き、感激して帰ってきます。私もその一人でした。
しかし、
実は学術的にこの山はほとんど何の根拠も無いのです。
実はシナイ山の候補地は幾つかあります。ジェベル・ムーサと言う名の山も複数あります。
そして現在のシナイ山は最も根拠の無い山であることが分かってきました。
それは次のような理由によります。
1.シナイ半島は歴史上常にエジプト領だった(1967年6月に起きた第3次中東戦争〔六日戦争〕によってシナイ半島がイスラエルに占領された後の和平交渉でイスラエルがあっさりシナイ半島をエジプトに返還したのも、聖書でアブラハムに神様が与えた領土にはシナイ半島は含まれていないからです)。
2.シナイ半島には銅とトルコ石の鉱山があり、古代エジプト時代には盛んに採掘が行われていた。そのために多くのエジプト軍が駐留していた。
3.現在のシナイ山は4世紀にローマ皇帝コンスタンチヌスの母へレナが勝手に決めた聖地の一つに過ぎない。
4.現在のシナイ山近辺にはイスラエルの100万を越える人口がキャンプする広い土地が無い。
5.モーセの出エジプトの痕跡になる遺物などはまったく発見されていない。
ところが最近になって
民間の考古学者※ロン・ワイアット(1933年6月2日 - 1999年8月4日)(タコ注 ※看護麻酔士)さんがシナイ山の候補地の一つだった
アラビヤ半島のラウズ山(タコ注:Jabal Al-Lawz ヤベル・エル-ローズ 難民の山ロウズ)
に行き、はっきりとした確証を発見しました。
しかし、サウジアラビヤ政府は考古学的な調査を許さなかったために、ワイアットさんたちは逮捕拘留され75日間も監獄に入れられ、釈放されたとき、全ての持ち物を取り上げられ、そこで見たことは一切発表してはならないと厳命されました。
実はサウジアラビヤはこの山をミサイル基地にする予定だったのです。標的はもちろんイスラエルでした。
ところが1988年資産家で冒険家のラリー・ウイリアムズとボデーガードのボブ・コーニュークは、ワイアットさんのチームの一人だった男からそこに莫大な財宝が埋まっていると言う話を聞き、非常な苦労の末にラウズ山に登りました。そして
そこに聖書の記述どおりの遺跡を発見しました。
それは彼らの事を書いた「隠された神の山」(ハワード・ブルム著1999年2月角川書店刊行)と言う本に書かれています。
1.山に登ることを禁ずる境界を示す積み石の列
2.金の子牛を祭ったと思われる大きな石の祭壇(砂漠にはいない牛の絵が描かれている)
3.イスラエルの12部族の為に立てた12の石柱
4.モーセの祭壇と思われる祭壇跡
5.エリヤが過ごしたと思われる洞窟
6.黒くこげた山肌
7.モーセが隠れた岩の裂け目
しかし、実はラウズ山はすでにサウジアラビヤのミサイル基地になっていて、(ここにラウズ山の写真を載せられないのは、そのせいです。)山は有刺鉄線で囲まれ、24時間体制で警備されていました。
彼らは非常な危険を冒してそこに入り、山に登り、命からがら脱出しました。財宝どころではなかったのです。
しかし、彼らは財宝以上の宝を発見しました。その山のおごそかな雰囲気と、神は居るという確信でした。彼らはクリスチャンとなりました。
以上引用終わり。
以下は
古代文明の後背地タブーク(Tabuk)
からの引用です。
□3.1.13 ヒスマー地方(Hasma region、切断面の山地)
ヒスマー地方(Hasma region)はタブーク(Tabuk)市の西に位置して居り、その重要な考古学的遺跡はその北西部のラウズ山(Jabal Al-Lawz、難民の山)の周辺にある。
ラウズ山(Jabal Al-Lawz タコ注:ヤベルエルローズ)はタブーク(Tabuk)から西北西に125 km離れ、
この地域では標高の一番高い山塊である。
この山塊はタブーク(Tabuk)の西から北へとサラワト山脈(The Chain of Sarawat Mountains)へつながり、更に北へジョルダン(Jordan)の涸れ谷ラム(Wadi Rumm)まで続いている。
この地域にはサムード(Thamudic)、ナバテア(Nabataean)および早期イスラームの碑文に加えて一万年前の岩壁画や碑文が散らばっている。
ヒスマー地方(Hasma Region)はその地理的な位置からナバテア時代(Nabataean Era)の紀元1世紀および紀元2世紀に通商が栄え、文明が発展した。それ以降にもこの地方の人々の為の通商は続きこの地域にアラビア人集落が永続的にあった事を示している。
以上引用終わり。
以上を簡単にまとめると
1.山に登ることを禁ずる境界を示す積み石の列
2.金の子牛を祭ったと思われる大きな石の祭壇(砂漠にはいない牛の絵が描かれている)
3.イスラエルの12部族の為に立てた12の石柱
4.モーセの祭壇と思われる祭壇跡
5.エリヤが過ごしたと思われる洞窟
6.黒くこげた山肌
7.山頂のサファイア
8.モーセが隠れた岩の裂け目
9.モーセが杖で叩くと大量の水がその裂け目から流れ出た山の麓の小高い石山にある岩石
10.足跡が刻みこまれた石
となり、
アラビア半島の付け根にあるヤベルエルローズ(ヤベルエルラウズ)こそ真のシナイ山であり、
コンスタンティヌス帝の母ヘレナがでっち上げたシナイ半島にあるシナイ山は偽物です。
出エジプト記の最後のルート

アカバ湾の真ん中辺りの
ここで海が割れて
モーセ一行はファラオの追跡から逃れます。
以下は
PT_088_Supplement_News_Article_Ja (1).pdf
より引用です。



エジプト考古学博物館

映画『十戒』より
同じ
アカバ湾の真ん中辺りの
ここで海が割れて
モーセ一行はファラオの追跡から逃れます。
以下は
PT_088_Supplement_News_Article_Ja (1).pdf
より引用です。
スウェーデンのカロリンスカ研究所のレナート・モーラー博士率いる国際チームが明らかにした。
海底からはエジプト第18王朝の戦車の車輪を閉じ込めた形の珊瑚が無数に発見されており、反論はほぼ不可能である。

イスラエルの民が渡った部分は、橋梁のようになっていて水深は 100 メートルほどだという。

神は吊橋のようにゆるやかに対岸とむすぶ海底の「橋」の上の水をどけられ、壁のようにそそり立たせたのである。
しかし、エジプト軍が同じように渡ろうとしたところ、一挙に海の水が元に戻り、すべてが呑み込まれてしまった。一瞬にして世界最強の軍隊が全滅した、と聖書は記す。
以上引用終わり。
海底からはエジプト第18王朝の戦車の車輪を閉じ込めた形の珊瑚が無数に発見されており、反論はほぼ不可能である。
イスラエルの民が渡った部分は、橋梁のようになっていて水深は 100 メートルほどだという。
神は吊橋のようにゆるやかに対岸とむすぶ海底の「橋」の上の水をどけられ、壁のようにそそり立たせたのである。
しかし、エジプト軍が同じように渡ろうとしたところ、一挙に海の水が元に戻り、すべてが呑み込まれてしまった。一瞬にして世界最強の軍隊が全滅した、と聖書は記す。
以上引用終わり。
エジプト考古学博物館
映画『十戒』より
同じ
以下は
出エジプト記の真実―モーセが紅海を割った奇跡や十の災いは歴史的事実か
からの引用です。


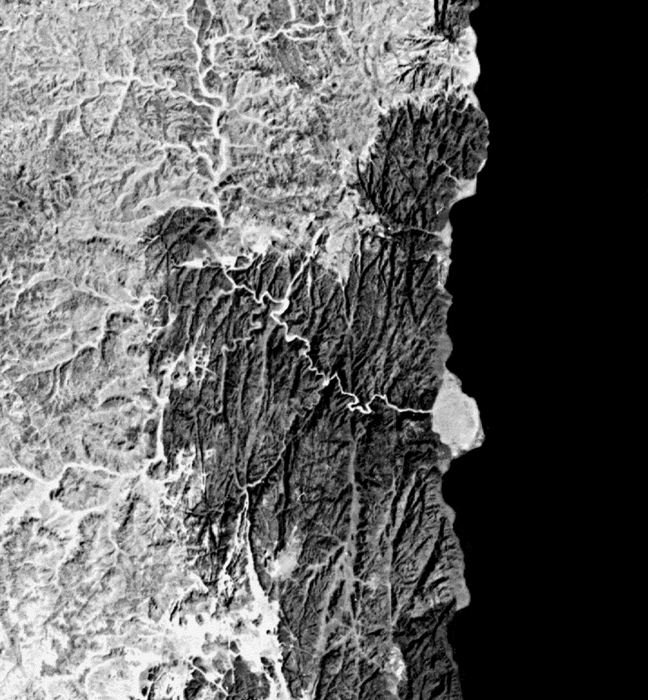



エジプトを脱出したイスラエル人は、女や子供も合わせると、合計約200万にも上る大群だった。したがって、もし聖書の記録が正しければ、200万の人間が宿営できるような広い場所が、紅海に面した場所(タコ注 アカバ湾)になければならない。
実際に、エジプト側の紅海の地形(タコ注 アカバ湾)を調べてみると、ちょうど200万人が宿営できるような広さを持つ、ヌウェイバという場所がある。聖書の記録の通り、イスラエル人全員が宿営できるような広さの場所は、たしかに存在しているのだ。
さらに、ユダヤ人の歴史家ヨセフスの証言によれば、彼らが追いつめられた宿営の場所は、険しい山々に囲まれていたようだが、その地形は、まさにヌウェイバと一致しているのである。
「ヘブル人に追いついたエジプト人は彼らを包囲し、近寄りがたい山々と海の間に閉じ込め、行く手を全てふさいだ。両側の険しい山々は海岸線まで来ていたので、逃げ場は無かった。」(ヨセフス)
▢紅海の海底で見られる車輪の形の人工物
「22 そこで、イスラエル人は海の真中のかわいた地を、進んで行った。・・エジプト人は追いかけて来て、パロの馬も戦車も騎兵も、みな彼らのあとから海の中にはいって行った。・・主は・・25 その戦車の車輪をはずして、進むのを困難にされた。27 モーセが手を海の上に差し伸べたとき、・・水はもとに戻り、あとを追って海にはいったパロの全軍勢の戦車と騎兵をおおった。残された者はひとりもいなかった。」(出エジプト14:22-28)
エジプト人が戦車とともに海の中を渡ろうとし、そこで溺死したのであれば、その海底の中に、戦車の残骸が残っている可能性がある。もし残骸が見つかれば、確かに神が紅海を分けたことの証明となるだろう。
調査チームは、ダイビングで海底を調査した。すると、ヌウェイバ付近の海底に、明らかに人工物だと断定できる、車輪のような形状のサンゴを複数発見した。(基本的に海底の固形物は、時間が経つとサンゴに覆われる。
また、同じような車輪の形状のサンゴは、対岸付近の海底でも見つかっている。したがって、これらの人工物の遺跡は、かつてエジプト人が、この海の底で戦車と共に滅びたことを裏付ける証拠と言えるだろう。
図
▢紅海の海底の地形
ヌウェイバ側と、サウジアラビア領となる対岸の付近で、同じ種類の遺跡が見つかる場所を線で結ぶと、ちょうど東西にまっすぐのラインとなる。
したがって、イスラエル人が渡った海底のルートは、このライン上となるはずである。さらに、このライン上の海底は、急な斜面や淵のない、なだらかな地形でなければならない。そうでなければ、大群が渡りきることは不可能だからだ。
調査チームが、測定器を使い、このライン上の海底の水深を調べたところ、興味深い事実を発見した。東西のライン上の海底の地形は、深い場所で水深500mほどになるが、傾斜は終始なだらかであり、急な斜面や淵は一切なかったのである。このような地形であれば、200万人の人々が歩いて渡ることは、難しくはなかっただろう。
これまでに紅海の海を割った奇跡の証拠として、(1)宿営場所の実在、(2)海底で発見される車輪型の人工物、(3)海底のなだらかな地形、の三つを取り上げた。これらの証拠を総合的に考えるなら、イスラエル人が紅海を歩いて渡った記録は、架空の伝説ではなく、歴史的事実であったと考える十分な理由があると言えるだろう。
以下はコチラから。
ヌウェイバの浜と呼ばれる東西4キkm、南北6km広さを持つ浜の衛星写真
ワイアット考古学博物館より
↑エジプト側の海底
↑アラビア半島側の海底
♣ノアの方舟♣

ノアの方舟を発見した
ロン・ワイアットが再現したノアの方舟
ロン・ワイアットが再現したノアの方舟
ノアの方舟 ロン・ワイアット物語
動画(画像2枚はこの動画から)


以下画像、リンクは
ロンワイアットによって発見されたノアの方舟

断面図
画像はコチラから





テネシー州マーシャル郡
ダラス・フォートワース国際空港DFWから約957km
動画(画像2枚はこの動画から)
以下画像、リンクは
ロンワイアットによって発見されたノアの方舟
断面図
画像はコチラから
1987年6月20日、
トルコ政府は
ノアの箱舟国立公園を
設立しました。
トルコ政府は
ノアの箱舟国立公園を
設立しました。
衛星写真
以下の画像はコチラから



石で作られた錨


大きい方が大アララト山
見る方向によっては富士山ソックリ

アルメニアの首都エレバン市内から見たアララト
エレバン観光に関しては
コチラ
コチラ
コチラ
日本からは一般的にドバイ経由かイスタンブール経由になります。

▢Wyatt Archaeological Museum
(ロン・)ワイアット考古学博物館
米国テネシー州マーシャル郡コーナーズビル
以下の画像はコチラから
石で作られた錨
大きい方が大アララト山
見る方向によっては富士山ソックリ
アルメニアの首都エレバン市内から見たアララト
エレバン観光に関しては
コチラ
コチラ
コチラ
日本からは一般的にドバイ経由かイスタンブール経由になります。
▢Wyatt Archaeological Museum
(ロン・)ワイアット考古学博物館
米国テネシー州マーシャル郡コーナーズビル
テネシー州マーシャル郡
ダラス・フォートワース国際空港DFWから約957km
JAL
KIX関空〜DFW
0645 1910 15時間45分 乗り継ぎ一回
DFW〜KIX関空
1030 1845 18時間15分 乗り継ぎ一回

テネシー州デイヴィッドソン郡(ナッシュビル)
ナッシュビル国際空港へ(約2時間)
以下は別口

米ケンタッキー州にあるクリエーション・ミュージアムに展示されている実物大のノアの箱舟
創造博物館HP

オランダに作られたノアの方舟Johan Huibers製作
動画3本
18億円掛けて作りました。
AFP BBニュースとは?
フランスに有る世界3大通信社の一つ。
AFPBB Newsは、AFP通信が配信する世界中のニュースをいち早く日本語に翻訳、編集した記事と写真を配信している。
以下は
KIX関空〜DFW
0645 1910 15時間45分 乗り継ぎ一回
DFW〜KIX関空
1030 1845 18時間15分 乗り継ぎ一回
テネシー州デイヴィッドソン郡(ナッシュビル)
ナッシュビル国際空港へ(約2時間)
以下は別口
米ケンタッキー州にあるクリエーション・ミュージアムに展示されている実物大のノアの箱舟
創造博物館HP
オランダに作られたノアの方舟Johan Huibers製作
動画3本
18億円掛けて作りました。
AFP BBニュースとは?
フランスに有る世界3大通信社の一つ。
AFPBB Newsは、AFP通信が配信する世界中のニュースをいち早く日本語に翻訳、編集した記事と写真を配信している。
聖書では、ノアの方舟のサイズが「長さ300キュビト、幅50キュビト、高さ30キュビト」と記載されています。
1キュビトは約44.5cmと計算すると、ノアの方舟のサイズは、長さ約133.5メートル、幅約22.2メートル、高さ約13.3メートルになります。
30で割ると4.55、5で割ると4.44、3で割ると4.43です。4.47333が平均値です。
以下は
からの引用です。
3,000平方メートル(900坪)の広さの土地に13.4 mの高さのビルが建造されたことになり、近代的な船では約15,000トン級の船に相当すると算出されています。(中略)
船体は短いと不安定で、長すぎると大波に乗った時真ん中から折れる危険性があります。幅・高さについても同様で、最高の安定性を得るためには相互に最高の比率を保っている必要があります。長い研究の結果、造船界ではタンカー級の大型船にとって最も高い安定性と強度を持つ形は、長さ・幅・高さの比率が黄金比と呼ばれる30:5:3であることが判明しました(「創造論の世界」久保有政著)。
この比率はノアの箱船の比率と同じであり、ノアの時代に主が教えて下さった知識に、人類は二十世紀後半になってやっと辿り着いたのです。
以上引用終わり。
▢AI による概要
「30:5:3」という比率の船は、造船界では「黄金比」と呼ばれ、特にタンカーなどの大型船に安定性や強度をもたらすことから用いられる設計比率です。
この比率は、長さ、幅、高さの順に示されています。
具体的に、この比率を持つ船の例としては、タンカーやバルクキャリア、クルーズ船などがあります。
▢黄金比の由来:
この比率は、長:幅:高=30:5:3というように、船の形状が海上で最も安定し、強度が保たれるように設計された結果、造船界で「黄金比」と呼ばれるようになりました。
▢タンカー:
大型のタンカーは、この比率を採用することで、液体の揺れや船体の変形を最小限に抑え、輸送中の安定性を高めることができます。
▢バルクキャリア:
バルク貨物船も、貨物の重量や積載量、海上の揺れを考慮して、この比率が採用されることがあります。
▢クルーズ船:
クルーズ船は、乗客の快適性や船体の安定性を高めるため、この黄金比を参考に設計されることもあります。
▢石油タンカー
『AIによる概要
石油タンカーで最も一般的なのはVLCC(Very Large Crude Carrier)で、全長約330m、幅約60m、深さ約29mです。』
30で割ると11m 、5で割ると12m、3で割ると9.66mで、10.887mを基準とすると黄金比率の近いですね。
【参考】
世界最大だったノック・ネヴィス
全長 458.45 m、型幅 68.8 m、深さ29.8m。
30で割ると15.281、5で割ると13.76、3で割ると9.14。12.727が平均値です。
戦艦大和
全長458.4m、全幅68.9m、深さ19.165m
30で割ると15.28 5で割ると13.78 3で割ると6.388
タンカーと戦艦は用途が違い過ぎますが、長さ幅が似てるのは興味深いですね。
▢ケープサイズバルカー
全長 291.98m
幅 45.00m
深さ 24.70m
30で割ると9.732 5で割ると5 3で割ると8.23
▢AIによる概要
新パナマックス船の主な特徴は以下の通りです(新パナマ運河の大きさによる制約で黄金比率にはなりません)。
長さ∶336.96m程度
全幅∶48.2m程度
深さ∶27.2m程度
30で割ると11.232m 5で割ると9.64m 3で割ると9.06m
それでも、9.977mを基準とすると、黄金比率に近いですね。
▢自動車運搬船
全長 199.95m
幅 32.20m
深さ 21.19m
30で割ると6.665、5で割ると6.44、3で割ると7.06
6.722mを基準とすると、ほぼ黄金比率に近いですね。
ワレニウス・ウィルヘルムセン(WW)トンスベルグ
全長 265.00m
幅 32.26m
深さ 33.22m
30で割ると8.833、5で割ると6.452、3で割ると11.07
ちょっと違いますね。
世界最大のワレニウス・ウィルヘルムセン(WW)9,300CEU型
全長228メートル
幅38メートル
30で割ると7.6m、5で割ると7.6m、3で割ると7.06m。平均値は7.42mで、ほぼ黄金比率です。
バルクキャリアのサイズ
ケープサイズ
280m 45m 18.2m
30で割ると9.333 5で割ると5 3で割ると6.06
パナマックス
229m 32.25m 14.43m
30で割ると7.633 5で割る6.45 3で割ると4.81
ハンディマックス
189.99m 32.26m 12.8m
30で割ると7.633 5で割る6.45 3で割ると4.81
パナマックス(旧パナマ運河の制約有り)とハンディマックス(立ち寄れる港の制約有り)の比率は同じですが、共に制約付きなのでノアの方舟の黄金比率には当てはまっていません。
コメント
カテゴリー
最新記事
(04/22)
(04/21)
(04/16)
(04/14)
(04/12)
カテゴリー
カレンダー
最新コメント
最新記事
(04/22)
(04/21)
(04/16)
(04/14)
(04/12)

